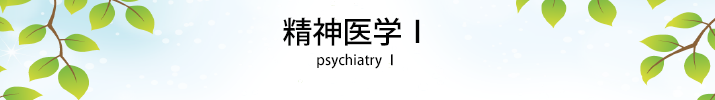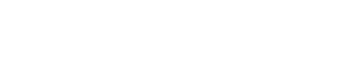予約制です contact us
ご予約・お問い合わせ
TEL 053-589-5153
FAX053-589-5173
浜松市南区恩地町355-1
午前の診療 AM8:30~AM12:00
午後の診療 PM2:00~PM 5:00
定休日:毎週水曜日・土曜日午後・日曜日・祝祭日
予約制です contact us
ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ
TEL 053-589-5153
FAX 053-589-5173
浜松市南区恩地町355-1
定午前の診療 AM8:30~AM12:00
午後の診療 PM2:00~PM 5:00
午後の診療 PM2:00~PM 5:00
定休日:毎週水曜日・土曜日午後・日曜日・祝祭日
MENU
精神医学Ⅰ
- HOME »
- 精神医学Ⅰ